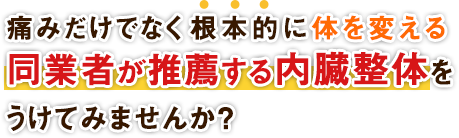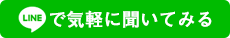足底の痛みには足のアーチを復活させるタオルギャザー体操がおすすめ
足の裏が痛むことは誰にでもありますが、痛みが治らないのは異常事態です。
本来なら、足裏は歩くために多少は痛んでもすぐに回復する様に出来ています。
痛みが解消されない人の多くは、足のアーチ構造が崩れています。
こちらでは足のアーチ構造の説明と、崩れてしまった足のアーチを復活させる体操を紹介しています。
足のアーチの作り
足の骨は28個あり、それらがつなぎ合う事で足の形を作ります。
足にはアーチ構造があり、足を裏から見ると土踏まずと呼ばれる部分があります。
足のアーチ構造は指の方から逆三角形になっており、土踏まずの内側を内側縦アーチと呼びます。
そして土踏まずの外側は、内側よりもやや低めで外側縦アーチと呼ばれます。
また指のつけ根を横断する形で横アーチもあります。
これらの三つのアーチを総称して足のアーチ構造と呼びます。

このアーチ構造は、足底への衝撃を吸収し、足関節から膝関節、腰までの負担を幅広く軽減します。
三つある足のアーチは一つでも働きが悪くなると、いわゆる扁平足のような状態になり身体の動きに支障をきたします。
痛みは出なくても、普段から足が疲れやすい人は足のアーチが崩れているかもしれません。
足のアーチは生まれつきではないので、子供の時に運動をして発達しても、大人になってからの運動不足や肥満などでアーチが崩れてしまう事もあります。
特に足や指を動かすことが少ない人は、足のアーチが崩れやすく扁平足になりやすいと言えます。
足のアーチを復活させるには
足のアーチは運動不足で崩れてしまいますが、鍛えればまた復活します。
ここで重要となるのは、足裏の筋肉よりもアーチの核となる舟状骨という骨につく筋肉です。
舟状骨には、
- 長母指屈筋(ちょうぼしくっきん)
- 長趾屈筋(ちょうしくっきん)
- 前脛骨筋(ぜんけいこつきん)
- 後脛骨筋(こうけいこつきん)
がついており、舟状骨の動きを調整します。
舟状骨を真下から支えているのが長母趾屈筋と長趾屈筋で、長母趾屈筋は親指へ、長趾屈筋は残りの4指へとつながり、足底のクッションの役割を果たします。
さらに舟状骨を上に引き上げるのが、すねから来ている前脛骨筋と、ふくらはぎから来ている後脛骨筋です。
この4つの筋肉が、きちんと働いていれば足のアーチは強くなり、疲れにくくなります。
そこでお勧めなのがタオルギャザー体操です。
やり方は、
- 椅子に座って足の下にタオルを起きます
- そのタオルをギュッと掴みます
- かかとは浮かさずにタオルを掴んだまま指先をゆっくりと持ち上げます
- そしてパッとタオルを離します
この動作を10秒位かけてゆっくりと行い、左右ともに10回ずつ繰り返します。
握る動作では長母趾屈筋と長趾屈筋が強く縮み、持ち上げる時には前脛骨筋と後脛骨筋が働きます。
筋肉は強く縮ませた後に、パッと力を抜く事で緩み柔軟性が高まります。
足のアーチを復活させよう!
治らない足の裏の痛みの多くは、足のアーチを復活させることで解消されます。
足のアーチは運動不足の人ほど崩れやすく、多くの人が偏平足になっています。
ですが、鍛えれば足のアーチは復活するのでぜひ体操を行って下さい。